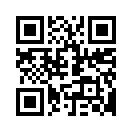笑わないのが面白い
2014年01月08日
無声映画が盛んだった頃、
チャップリンとキートン、そして
丸い黒ぶちメガネで知られるロイドとともに
世界3大喜劇王と呼ばれていた。
チャップリンは、あの口ひげ、あのスタイルを
誰でも思い浮かべることができるほど、
今でもよく知られている。
だけど、バスター・キートンを
すぐに思い浮かべることができる人がいるならば、
その人は、かなりの映画通。
でなければ、かなりの年齢。
どちらの映画も、観客を爆笑の渦に巻き込むほどだったが、
作風に大きな違いがあった康泰導遊。
チャップリンが、
それぞれの状況に応じて表情を変えるのに対して、
キートンの特徴は、
喜怒哀楽の表情を出さないことだった。
自分は、笑わせるのが仕事。
笑うのは観客、といったところだろうか。
人を笑わせるのに、自分は笑わない職業で言えば、
「幇間(ほうかん)」と呼ばれる人たち。
いわゆる「たいこもち」で、
ダンナ衆にくっついて気の利いた話し相手になったり、
芸をしたり、笑わせたりする職業だが、
本人は決して笑わなかった。
笑うのは相手、ということだろう米蘭旅遊。
シェイクスピアの喜劇
「お気に召すまま」に出てくる
道化であるタッチストーンは、
この喜劇の笑いの半分をとるが、
これを演じる役者は笑わないのが通例になっている。
このタッチストーンの役柄は道化であるが、しばしば
チクリと刺すような耳の痛いセリフを言う。
ばか者は自分を賢いと思い
賢者は自分を愚かだと自覚する
たしかに、笑いながら言えるセリフではない、、。

チャップリンとキートン、そして
丸い黒ぶちメガネで知られるロイドとともに
世界3大喜劇王と呼ばれていた。
チャップリンは、あの口ひげ、あのスタイルを
誰でも思い浮かべることができるほど、
今でもよく知られている。
だけど、バスター・キートンを
すぐに思い浮かべることができる人がいるならば、
その人は、かなりの映画通。
でなければ、かなりの年齢。
どちらの映画も、観客を爆笑の渦に巻き込むほどだったが、
作風に大きな違いがあった康泰導遊。
チャップリンが、
それぞれの状況に応じて表情を変えるのに対して、
キートンの特徴は、
喜怒哀楽の表情を出さないことだった。
自分は、笑わせるのが仕事。
笑うのは観客、といったところだろうか。
人を笑わせるのに、自分は笑わない職業で言えば、
「幇間(ほうかん)」と呼ばれる人たち。
いわゆる「たいこもち」で、
ダンナ衆にくっついて気の利いた話し相手になったり、
芸をしたり、笑わせたりする職業だが、
本人は決して笑わなかった。
笑うのは相手、ということだろう米蘭旅遊。
シェイクスピアの喜劇
「お気に召すまま」に出てくる
道化であるタッチストーンは、
この喜劇の笑いの半分をとるが、
これを演じる役者は笑わないのが通例になっている。
このタッチストーンの役柄は道化であるが、しばしば
チクリと刺すような耳の痛いセリフを言う。
ばか者は自分を賢いと思い
賢者は自分を愚かだと自覚する
たしかに、笑いながら言えるセリフではない、、。